 |
|
APRC MACHINE DETAILS |
 |
2007年の「Rally Hoikkaido」で投入されたニューマシン。
ルーフを白く塗装しているのは暑さ対策のひとつ。
|
 |
室内はノーマル車の面影を強く残している。しかし良くみるとセンターに三連の追加メーターが備わっていたり、車両規定に従った公認サイドブレーキが装着されていたりという違いを見て取れる。
|
 |
キャビンは牽強なロールケージで守られている。もちろんこれもFIA公認部品のひとつ。
|
 |
ナビシート前のダッシュボードには、ラリーマシンを象徴する装備のひとつである「ラリー・コンピューター」が装着されている。ここには走行距離や時間が表示されるほか、計算機能も有している。
|
 |
伝統の水平対向4気筒エンジンはインタークーラーターボで武装している。
|
 |
ルーフベンチレーションを室内側から見たところ。必要に応じて開放し、走行風を室内に取り込んでいる。
|
 |
キャビン後部からトランクスペースを通って左リアフェンダーへとダクトが通じている。ここを空気が通ることで車室内の熱気や埃が抜けていくようになっている。
|
 |
装着するタイヤはADVANラリータイヤ。2006年の「Rally Hokkaido」からはプロトタイプを使用、柳澤選手も高い信頼を寄せている。 |
|

 |
 |
柳澤宏至 選手 |
1969年・神奈川県出身。
2006年からAPRCにフル参戦を開始、シリーズ2位の成績をおさめた。 |
 |
 |
 |
長瀬 努 監督 |
| クスコレーシングワールドラリーチームの監督としてAPRCを戦う。自身もドライバーとして全日本ジムカーナ選手権のタイトルを獲得した経験を有する。 |
|
−「Rally Hokkaido」から新車を投入しましたが、その背景とは?
柳澤選手 :
まずは改めて全日本戦とアジア・パシフィック・ラリー選手権(APRC)の違いを知ると、新車を投入した理由をよりお分かりいただけると思います。
APRCは全日本戦と比較すると圧倒的に走行距離が長いのです。また暑さの厳しい地域での戦いも多いので、マシンには想像以上の負担がかかります。
長瀬監督 :
これまで使っていたのが2006年の「Rally Hokkaido」にデビューさせたものですから、丸一年での入れ替えということになりますね。
シリーズを転戦するために、ラリーマシンは世界中をまわっています。
そのスケジュールを組み立てていくと、北海道での新車投入となるのです。
海外へは船便のコンテナで運ぶのですが、赤道を越えるときは大量の除湿剤を入れなければならないほどに湿気の影響を受けます。そのままにするとゴム類などへの悪影響があるので、そのような環境を避ける輸送スケジュールなども考慮してマシン開発を行っています。
柳澤選手 :
先にシェイクダウンをミニサーキットで行ったのですが、シェイクダウンの日付が'06年にデビューさせたマシンと同じ日でした。
自分が走行するために'06年に取得したコースライセンスの日付がちょうど一年前のもので、ちょっとビックリしましたね(笑)。
−全日本ラリー選手権のマシンとは中身は全く異なる?
柳澤選手 :
CUSCO RACINGではAPRCと全日本戦の両方にスバルインプレッサで参戦しています。
それらの中身が「全く異なる」のかといえば、実は現在のAPRCマシンは全日本のN車両と大きくは変わりません。
しかし、車の造り方としては距離が長いので強度を高くすることを重視します。モータースポーツでは軽量化が至上命題のような部分もありますが、APRCについては多少重量が増えるとしても補強を入れたりもします。
車両のバランスという面では、80リットルほどの容量をもつ安全燃料タンクを備えていますが、これをフロアに設置しています。やはり重量物ですから、なるべく低い位置に持っていきたいということです。
トランスミッションは5速と6速が設定されていますが、これらを大会によって使い分けています。ニュージーランドのような高速型の戦いでは一部で6速を使います。トップスピードでは200km/hくらいをマークするでしょうか。さらにいえば5速での全開コーナーリングなどという場面もあるのですが、さすがにこれは日本ではありえないハイスピードコーナーですね。
|
| |
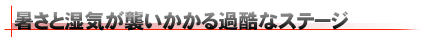 |
|
−開催地の"暑さ"はどのようなものですか?
柳澤選手 :
例えばマレーシアでの戦いでは少し早めに現地入りして身体を暑さに慣らすようにしています。実際は去年もそうでしたが、気温よりも高い湿度が過酷ですよね。
樹木が生い茂っているプランテーションの中を走るのですが、風がないので湿度は80%、車内の温度は50度以上になってしまいます。
−そうなると、暑さ対策は必須ですね。
柳澤選手 :
車にとっては吸気温度も高くて厳しいですよね。
室内の温度を下げるためには、ルーフに備わるベンチレーションから風を取り込みます。さらに室内に入った風がきちんと車外に抜けるように、キャビン後部にダクトを設けて熱の"こもり"を防いでいます。これは熱のほかに車内の埃を抜くという効果もあります。
ドリンクも飲めるようになっていますが、スペシャルステージ(SS)中は余程長いストレートでなければ飲めませんね(笑)。だから、実際にはリエゾンで飲むことがほとんどです。
|
| |
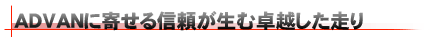 |
|
−インプレッサのライバルといえば筆頭はランサーですが、違いとは?
長瀬監督 :
一般的にコーナーリングが得意なインプレッサに対してトップスピードの速いランサーというイメージがありますが、確かにトップスピードの差は小さくないですね。10km/h以上の差がある場合もありますし。
柳澤選手 :
190km/hあたりから"伸び"が鈍るので、ドアミラーを畳んで「空気抵抗を減らしてやる!」なんてやってみたりもします(笑)。あとは暑くてもちょっと我慢してルーフのベンチレーションを閉じてみたり。
−APRCで使っているタイヤについての印象は?
柳澤選手 :
海外戦ではADVAN A035eを使ってきました。国内戦で使っていたADVAN A035と比べると、剛性感の高さを感じますね。"しっかり感"の高さは、海外の道でセットアップしたタイヤであることを実感させてくれます。
また、APRCでは状況に応じてタイヤに溝を入れる「グルービング」が認められてますが、これをやりやすいというのも大切なポイントです。
状況に応じたコンパウンドの選び方も勝敗を左右する大きなファクターですが、高速で過酷なAPRCですからタイヤに対する信頼性の高さは重要で、ADVANはその点でも満足するパフォーマンスを見せてくれています。
−新しいプロトタイプのラリータイヤについては?
柳澤選手 :
2006年の「Rally Japan」からプロトタイプを装着していますが、これはADVAN
A035eと比べて更に剛性が向上しています。
まさにタイヤの進化を感じているのですが、まだまだ更なる進化をしてくれるという期待感も持っています。
APRCは走行距離が長いので、摩耗とグリップのバランスが高い次元で求められますが、ADVANの戦闘力は一線級にあると言って間違いないでしょう。
|
| |
2007年の「Rally Hokkaido」では強豪勢がひしめくなかで4位フィニッシュを飾ったCUSCO
RACING。
次回、最終回ではAPRC、そしてラリーの魅力についてお聞きした内容をご紹介します。
【>> vol.3はこちら】 |
|